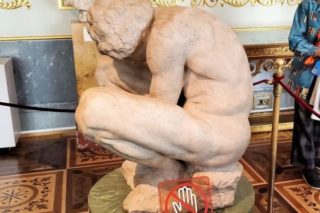ロシア旅行記:3日目
阪急交通社ツアー「お1人様参加限定:ロシア7日間」
-2020年3月12~18日
ロシアの中心部
ここはモスクワ市内でも中心部にあるクレムリンで、その城壁の西側にあるアレクサンドロフスキー庭園(Александровский сад)にまずはやって来ています。
モスクワの中心部にて
こちらの2014年に建てられた像は、1800年代初頭にロシア皇帝だったアレクサンドル1世(Александр Ⅰ)である。彼の時代にナポレオンが大軍勢を率いてロシア遠征し、最終的にナポレオン軍は敗走していくのである。
そのアレクサンドル1世像の目の前には、こちらのレリーフも一緒に造られている。ロマノフ王朝時代の銅像や紋章などは、1917年に起こったロシア革命時に破壊されたものが多いので、このように今見られるロマノフ王朝の皇帝などの像は最近建てられた物が多い。
アレクサンドル1世の向かい側に座る、同時期にロシア正教の修道士だったサロフの聖セラフィム(Серафим Саровский)の手だけはピッカピカになっている。これはここを通る人達が彼の手を触っていくからだと思う。
そしてアレクサンドロフスキー庭園内を歩いて、辿り着いたのがクレムリンでも南西にあるボロヴィツカヤ塔(Боровицкая Башня)の前。
このロシアを訪れたのは2020年3月中旬で、世界的に観光客が激減しだしていた頃合い。特に中国人観光客は団体での出国が禁止されていたので、いつもは大勢の中国人観光客で溢れるロシアでは全然見かけなかった。
そんなモスクワでも午前10時前には、このようにクレムリン内の武器庫を見学する長蛇の列が出来ていた。「今日はあまり外の見学が少ないです!」と聞いていたので、あまり着込んでいなかったのでこの列に並んでいる時は少し寒かった。。

クレムリンの武器庫見学は、コロナ禍の前はもっと混み合っていたのよ!
クレムリン内部へと入場する
そしてこちらの入場ゲートで保安検査を受けて、待望のクレムリン内へと入ってきました。ただこのクレムリン内も警備する兵隊さんが多いのかと思っていたけど、今では監視カメラが沢山取り付けてあるので、あまりその辺を巡回する兵隊さんは見かけなかった。
クレムリン内の武器庫の見学
さてこれから見学するのは、このクレムリン内の見学でも一番重要な武器庫(Оружейная палата)です。ただし武器庫と言っても武器ばかりが置かれているのではなく、元々武器庫として使われていた場所に、今ではロマノフ王朝時代の宝飾品などが沢山保管されている場所なのです。
まずは入口を入った先で上着を預けます。ロシアを初めて訪れる外国人が感じるのが、”ロシア人は愛想笑いをしない”事だという。
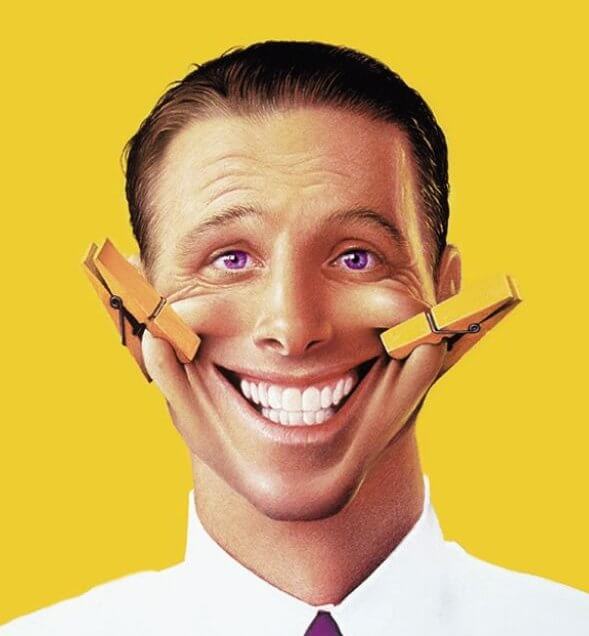
上着を預けると、引き換えにこちらの札を貰います。そして帰る際にこの札を渡して、上着を返してもらいます。
そして途中にはお土産物屋コーナーなどもあり、日本語の本なども売っています。
この建物が元々造られたのは1485年で、当初はここで武器や鎧などが造られていたという。その後ここで武器などを造るのが止められて、ロマノフ王朝の宝物などが置かれるようになる。
そして19世紀に入るとこの武器庫が、博物館として貴族に解放される。その後1918年以降は一般の人々が見学できるようになった。なおロシア革命の際のどさくさに紛れて、盗まれて転売された物もあるそうだ。
今のこの内装は皇帝ニコライ1世のお抱え建築家である、コンスタンチン・トーン(Константин Тон)によって1851年に完成し、”ビザンチン・リバイバル様式”(Byzantine Revival architecture)という建築スタイルで、この建物の横にある大クレムリン宮殿と同時期に建てられた。
この”ビザンチン・リバイバル様式”というのは、5~11世紀のビザンチン帝国時代の建造物の特徴を取り入れた新ビザンチン主義とも呼ばれ、モスクワ市内にある「救世主キリスト大聖堂」(Храм Христа Спасителя)も彼の設計である。なお44年掛かって造られた救世主キリスト大聖堂はソ連時代に壊されてしまうので、現在見られる大聖堂は再建された物で、残念ながらコンスタンチン・トーンが設計した建物を模倣して造られたものであるが。
そんな武器庫の入口階段に飾られている肖像画は、”現代ロシア人が一番尊敬する歴史上の人物”というアンケートで一番に名前が上がるピョートル1世(Пётр I Алексеевич:1672年生~1725年没)である。ピョートル大帝とも呼ばれる彼は、王位にあるにも関わらず西ヨーロッパに2年程視察に赴き、オランダなどで造船技術を学んだ。そして北の湿地帯だったサンクトペテルブルクを大工事で都市に造り替え、首都をモスクワから移した人物でもある。
武器庫に置かれている展示品は、この階段を登った先に置かれているがこれ以上先は残念ながら写真撮影が禁止されている。
だからギリギリの場所までは、写真撮影して粘ってみた。
今でこそキャンドルライトは電気になっているが、昔はこんなのも全部ロウソクだったのだろう。だから毎日何千本というロウソクを交換していたのだろう。。

昔はロウソクの火を付けたり消したりなどのロウソクを管理する、専門的な仕事もあったのよ!
こちらの絵はロシアが動乱の時代にあった17世紀初頭に起きた、ロシア・ポーランド戦争(Polish-Muscovite War)の時の様子を描いた絵画。ロシア軍を先導するポジャールスキー公と、商人だったミーニンが中心に描かれている。
こちらの間には4人の女帝が現れた18世紀の時代に、彼女達が着たという豪華な衣装の数々が展示されている。贅沢な暮らしをしていたエカテリーナ2世(Екатерина Ⅱ Алексеевна:在位1762~1796年)は、実に10,000点を超える衣装を造らせていたとか。。
武器庫の見学はこちらの階段を登って行きます。しかしここから先は全て写真撮影が禁止です。
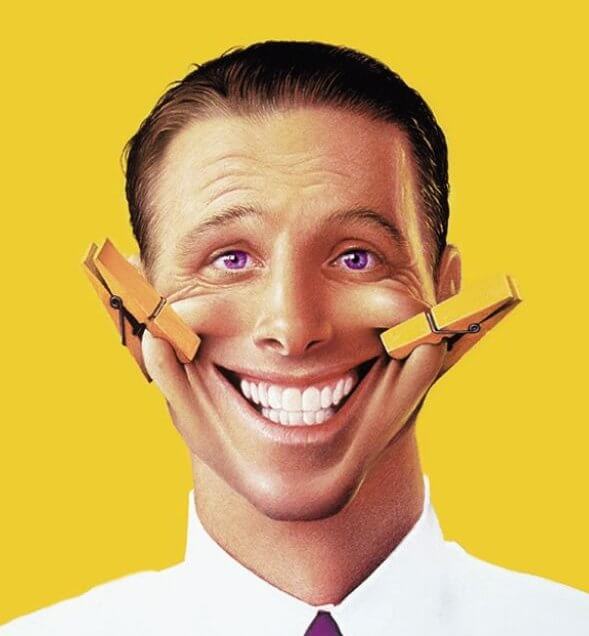



約1時間を掛けて武器庫内に保管されているロマノフ家のお宝の数々を見学しました。数千点に及ぶ展示品はじっくり見ると、2~3日は必要な位でした。こちらのオバサンはたどだどしい日本で説明してくれた、モスクワの現地ガイドさんのマリーナさん。
クレムリン内の見学でも一番見応えのあるのは、やっぱり色んな度を越えたお宝が収められている武器庫。もっと観光シーズンになってくると、本当にいつ入れるか分からない位の長蛇の列が出来ているという。。
正面奥にはこのクレムリンに入ってきた際に通ったボロヴィツカヤ塔、更に奥に見えるロシア正教の建物は武器庫や大クレムリン宮殿などを設計したコンスタンチン・トーンが造った救世主キリスト大聖堂である。
ちなみにこのボロヴィツカヤ塔などのクレムリン内の尖塔の先に赤い星が付けられているのは、ソ連時代の1937年からである。それまでのロシア帝国時代には、ロマノフ王朝の象徴である”双頭の鷲の紋章”の彫刻が飾られていたのである。
そしてこちらに見える大きな宮殿が、コンスタンチン・トーンが造った大クレムリン宮殿(Большой Кремлёвский дворец)である。
1849年に完成した建物で、約2万平米に渡る敷地と総部屋数は700室を超えるという。
主に外国の君主などを迎えた時の迎賓館的な役割をする宮殿で、外装だけ見ると3階建てのようだけど内装としては2階建てだそうだ。
そしてこの先はスライム型(丸玉型とかも言うけど)の屋根が金ピカになっている、ロシア正教の建物ゾーンとなります。
こちらはアルハンゲリスキー大聖堂(Архангельский собор)と呼ばれる、1508年にベニス出身のイタリア人建築家アレヴィズ・ノーヴィによって建てられた、大天使ミハエルを祀った大聖堂である。ここにはピョートル大帝以前のロシア皇帝達の遺骨が納められている場所でもある。
こちらはタイニツカヤ塔(Тайницкая башня)で、元々は1485年に造られたがその後解体され今見られるのは1783年に再建されたもの。

ちなみにこの塔には地下通路があり、クレムリン内から脱出できる抜け穴があったそうだよ!
この辺りは大聖堂広場(Боровицкая площадь)と呼ばれていて、周囲にはロシア正教の建物が沢山乱立するエリアとなっている。
大クレムリン宮殿の真横に建てられているのは、ブラゴヴェシェンスキー聖堂(受胎告知聖堂とも:Благовещенский собор)。1489年に大公イヴァン3世によって造られて、大公(ツァーリ)の洗礼や婚儀などが行われる場所でもあったという。
こちらは先程斜めから見たアルハンゲリスキー大聖堂(Архангельский собор)。この辺りの建物はロシア革命時に砲弾を浴びて建物は損壊し、ソ連時代は宗教弾圧されていたのでこれらの聖堂ではロシア正教は活動出来なかった。そしてソ連崩壊後にこれらの建物は、やっとロシア正教に返還されるのであった。
こちらはウスペンスキー大聖堂(Успенский собор)で、1479年にイタリア人建築家にイヴァン3世が建てさせたもの。歴代皇帝の戴冠式がここで行われており、現在でもロシア大統領の就任式にも使われる場所である。
大聖堂広場の景色 動画
イワン大帝の鐘楼(Колокольня Ивана Великого)という、1508年に高さ約60mで造られた建物で、その後1600年に改築されて現在の高さ81mとなった。
1883年に救世主キリスト大聖堂が造られるまでは、このイワン大帝の鐘楼はモスクワで一番高い建物だったそうだ。ちなみに内部にある300段を超える階段を登って上に行けば、展望台からの景色が見れるようだ。
このウスペンスキー大聖堂はモスクワ近郊の街、セルギエフ・ポサードにあったウスペンスキー大聖堂のモデルでもある。
こちらの入口周辺には17世紀に描いたとされるフレスコ画で、聖母マリアや聖人などが描かれているのが見える。なおこのウスペンスキー大聖堂内への入場は、この入口ではなく左奥からの入口になる。
大聖堂の屋根の金は、やっぱり青空だと一段と輝いて見える。現地ガイドのマリーナさんは盛んに「24カネ・・・24カネ・・・」と呟いていたけど、それは24金(キン)の意味だった。。
こちらの石造りの建物も15世紀末に建てられた、グラノヴィタヤ宮殿(рановитая палата)という戴冠式後の祝いや諸外国からの使節団などを持て成した場所。
こちらの建物は「十二使徒聖堂」(оерковьДвенадцатиАпостолов)。屋根の色が金色ではなく銀色なのは、イエスキリストへの聖堂ではなく、ロシア正教の聖人への聖堂を意味しているそうだ。
中央奥に煙突のように何個もの屋根が突起しているのは、ヴェルホスパッスキー聖堂(Верхоспасский собор)。1636年に造られた建物で、屋根には11個の突起が造られている。
こんな旅はまた次回に続きます!
よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!
↓↓↓↓ロシア旅行記:初回↓↓