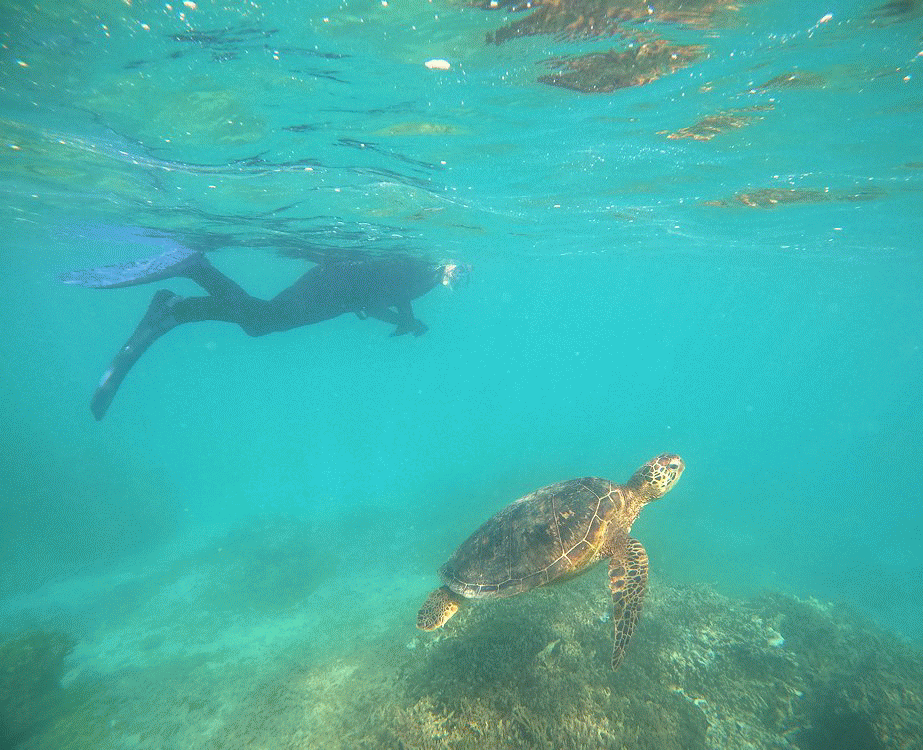奄美大島旅行記2020年-㊴
旅行期間:2020年10月1日~5日
(Kakero Island and Heart Bay seen from Manenzaki Observatory in the dusk [Amami Oshima Travelogue ㊴].)
明るいうちに景色は見ておけ!
さて夕暮れを迎えるにつれて、段々と波が強く打ち寄せるようになってきたホノホシ海岸。もう少し荒波が打ち寄せて、その波に揺られて轟音をなびかせる丸石群を見ていたかったけど、暗くなる前に次の目的地に行かないと景色スポットが多い奄美大島は、真っ暗な状態では全然その景色を写真に撮れなくなってしまうのだ。。
という事で駐車場から車に乗って、今日の最終目的地である瀬戸内町の古仁屋港へと向かう事にする。そして相変わらずこの池のようになっている場所に、電柱が並べられている光景が何とも摩訶不思議に見える。まあこのように実際にこれだけの電柱がわざわざこの水の中に埋められているという事は、そうするだけの理由があるのだろうが。。
ちなみにネットで検索してみるとこの池は海老の養殖場らしく、この沢山水中に設置されている電柱は水中に設置されている酸素を送り込む機械に電気を送る為用だそうだ。。
マネン崎展望台にて
そして「日が暮れる前に古仁屋港に着かないと・・・」と思っていたけど、道の脇にこのような「マネン崎展望台」があったのでいつもの習慣で寄り道してしまった。。
住所:鹿児島県大島郡瀬戸内町大字嘉鉄
ここマネン崎展望台は、目の前に大島海峡を挟んで向かいにある加計呂麻島を眺めれる景観スポット。ただしこのようにここの展望台に着いた時点で黄昏時も終わり頃になっているので、古仁屋に到着できるのは暗くなってからだろう。
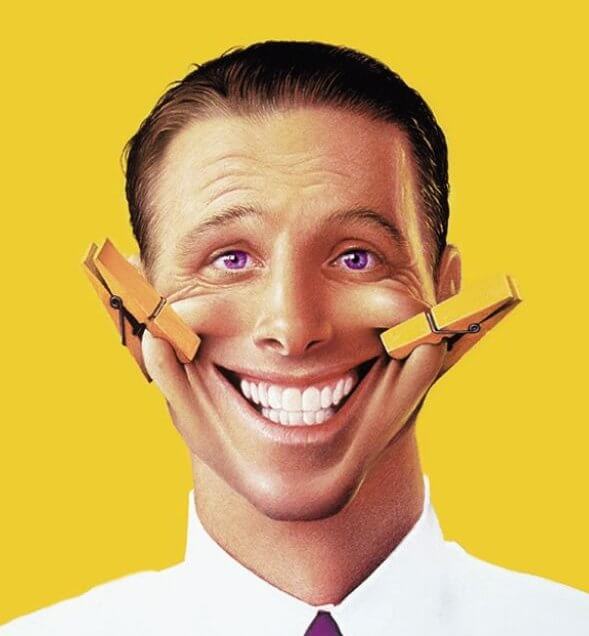
展望台が目の前にあったら、見逃す訳にはいかないからね!
この展望台の一角にはこのように同窓会の記念碑が置かれていた。わざわざこんな観光客が訪れるような場所の、しかも目立つ所に設置しなくてもいいと思うけど。。
このマネン崎展望台からは、日中の晴れた時間帯には綺麗な景色が見えて、しかも満潮時には大小の渦が加計呂麻島との間の大島海峡で見る事もできるという。
ただ晴れた日中は気持ちがいい場所なんだろうけど、このように陽が沈んで黄昏時も終わりを迎えている頃の展望台の景色は微妙であったが。。
こちらの海峡の先に見えているのが加計呂麻島で、都会からの移住者の割合が意外と高い島だという。都会の喧騒を逃れてのんびりと自然溢れた環境で暮らしたい人がやって来るけど、当然の如く都会の便利さはほぼ皆無なので、それを承知した上で移住しないと長居はできない。
左側に見えているのは奄美大島側だけど、その岬の先端まで楽に行ける道はないようだ。観光客はさっきのホノホシ海岸か、その近くにあるヤドリ浜という海岸までしか行かなくて、その先の岬先端に行ける道もマップには載っていない。
マネン崎展望台からの眺め 動画
本当はカヌーのお姉さんがオススメしてくれた古仁屋港からの夕焼けを見たかったけど、ここからでも僅かばかりの黄昏時を眺める事が出来たので、これはこれで良しである。それにこの奄美大島滞在5日間では、基本的に晴天が続いたのでそのような素晴らしい日を過ごせただけで幸せである。
このマネン崎展望台はさっき見た加計呂麻島が見える西側の展望台以外に、東側の方にも展望台が造られているのが見えている。なおここでも駐車場にあるのはボクの車だけで、こんな時間に展望台を訪れる客はなかなか居ないようだ。。
こちらの西側に設置されていた展望台は奄美大島でも珍しく、バリアフリー対応のスロープが設置されていた。それと大きなリュウキュウ松も見えている。
このマネン崎展望台は嘉鉄集落付近にあるので、ここからはさっき見えた「ハートが見える風景(嘉鉄ハート湾)」も見られるようになっているという。それとこの地図を見ていると、隣にある加計呂麻島までは結構近そうに見える。加計呂麻島までは橋は繋がっていないので、基本的には船しか交通手段はないようだが。
このように奄美大島の観光スポットでは珍しくバリアフリー対応がしてあり、このような車いす用駐車場枠も見られた。
ここには1本大きな松が周囲の景観を見下ろすように立っているのが見える。恐らく海沿いの高台で浜風が強く当たる場所なので、その風に耐えてしっかりと根を張っているのだろう。
ただこのような松もいつかは枯れる日が来る。植物も人間より長生きする種類もあるけど、最後には細胞が死滅して枯れてしまう運命にある。だから余計に生きている時にしっかり葉や花を咲かせるのである。
こちらはさっき右側の高台から眺めた「ハートが見える風景(嘉鉄ハート湾)」を、ここ西側のマネン崎展望台から見た景色。もう少し明るい時間帯であれば綺麗な色をした湾が見えたのだろうが、暗くなってくるとあまり綺麗に見えなかった。。
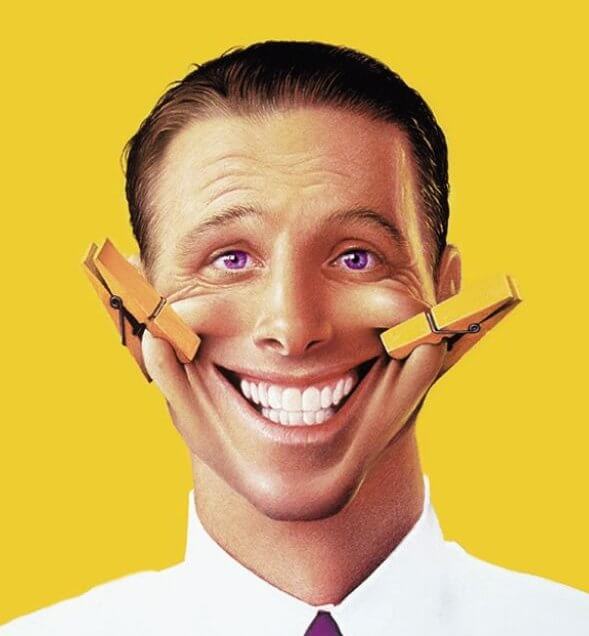
やっぱり景色は明るい時間帯に見るに限ります・・・
こちらにはわざわざこのような屋根付きの小屋まで造られていて、下にはテーブルや椅子などと共に奥には何かのパネルが置かれているのが見えている。
この「アマミホシゾラフグ(奄美星空河豚)」という新種のフグは、2012年頃に新しく発見された種類だという。元々はこの辺りの海の海底でミステリーサークルのような物が発見され、その調査をしていたらこのフグに辿り着いたという。なおこのミステリーサークルはオスの求愛行動の一環で、立派な巣を作ればメスがそれを見て寄って来るとそうだ。だからアマミホシゾラフグのオスは子孫を残すのに、この巣を綺麗に作る能力が求められるという訳。
この奄美大島には日本で確認されている動植物でも他の地域に比べると、その割合に占める種類が多くて、温暖な島国となっている影響もあって昔から独特な生態系が今でも残されている。
ハート湾が見える展望 動画
それにしてもちょっと幹が折れ曲がっているので弱々しく見える松だけど、このような風の強い場所に立っているからには芯がしっかりしているのだろう。。
瀬戸内町の古仁屋港にて
さてマネン崎展望台に寄り道した影響は大きくて、最終目的地である瀬戸内町の古仁屋港周辺に到着した時には、このようにすっかりと周囲は暗くなってしまっていた。
そんな瀬戸内町の大きな建物の前で照明に照らされている展示が見えたので、夜の昆虫ばりに近寄ってみた。ここは「瀬戸内町きゅら島交流館」という公民館になっている場所だそうだ。
そんな照明に照らされていた、こちらの青い物体は「ルリカケス(瑠璃橿鳥)」という、この奄美大島と近くの加計呂麻島・請島だけで見られる固有種のカラスの一種。このルリカケスは国の天然記念物となっており、一時は生息数が激減して絶滅危惧種に指定されていたけど、今では捕食するマングースなどの駆除が進んで個体数が増えてきているという。なお湯湾岳が主な生息地で運が良ければ、見る事もできるそうな。
こちらは「アマミノクロウサギ(奄美野黒兎)」で、こちらも絶滅危惧種に指定されている。こちらもマングースの導入や自然環境の破壊という、人為的な影響で個体数を減らされた可哀そうな動物である。。
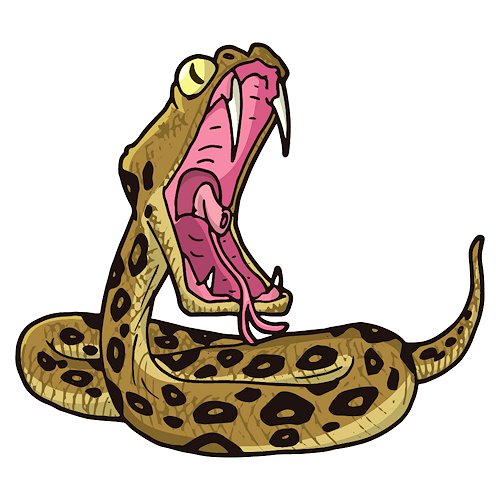
ホント、人間って滅茶苦茶な事ばかりするから大変ブ~~!(怒)
そして古仁屋港の方へと車を走らせるが、すでに18時30分を過ぎていたので港は真っ暗。この辺りにあるハズの「せとうち海の駅」を探しながらウロウロと進んできたけど、その海の駅は既に閉店で建物は真っ暗となっており、この突き当りにあった船で行き止まってしまった。。
う~~ん、夕陽は見れなかったけど、このように僅かながらの黄昏時を見る事が出来たので、これはこれでわざわざ古仁屋港まで来て良かったと思う。あとはせっかく港にやって来たので、この辺りで海産物が食べれるお店で晩飯を食べれれば、もう思い残す事はない。
こんな旅はまた次回に続きます!
よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!
↓↓↓↓奄美大島旅行記:初回↓↓