東京旅(2022年11月)-31
訪問:2022年11月中旬
どれが二重橋?
かつて江戸幕府の中心地だった江戸城跡は、今では天皇陛下が普段暮らす「皇居」となっている。
そんな皇居の中でも特に有名な場所が、西の丸入口となっている「正門」周辺に架かっている『二重橋』という橋。
この正面に見えている石造りの眼鏡橋が『二重橋』だと思ったが、正確にはこの橋は「正門石橋」という名前のようだ。
皇居周辺にて
この西の丸周辺にある皇居入口となっている正門は、天皇家専用の出入り口となっている為に一般人は基本立ち入りできない場所。

堀にも飛び込めないぜい!
この橋周辺では今から約100年前の大正時代に爆弾が投げつけられる事件などもあった影響で、このようにしっかりとした石が積み重ねられている詰所も見られる。
この江戸城跡は皇居として天皇一家が普段生活している場所でもあるので、周辺には警護している「皇宮警察の皇宮護衛官」が厳しい目でフラフラしている人を監視している場所ともなっている。

アンタも警戒されてるデ!(笑)
今まで「二重橋」という皇居の橋の名前を聞いた事がなかったけど、オカンの説明でこのアーチ状の橋がてっきりその二重橋だと思っていた。
ちょっと調べてみると、どうやらこの正門前に架かる橋ではなく、更にその内側に架かっている橋が昔に橋桁を上下2重にした設計だった為に、その外観から「二重橋」と呼ばれていたとか。
ただ、今見られるこの「正門石橋」の西側にある、そのかつて二重橋と呼ばれた橋も明治時代に鉄橋に架け替えられた為に、”二重橋”というイメージではなくなってしまった。
こちらが正門石橋の西側にある、かつて二重な外観の橋が架かっていた「正門鉄橋」。
このように今では”二重”という外観ではすっかりなくなっているので、初めて見た人にとっては「どこが二重橋??」と思ってしまう光景ともなっている。。
この皇居正門となっている立派な門は、「西丸大手門」として江戸時代に造られた櫓門。
この門もかつては二段の桝形構造となっていたが、今ではその外側の門は解体されて、西洋風な電灯が並ぶ入口となっている。

「明治時代初期の西丸大手橋」—「二重橋」Wikipediaより引用&カラー加工済
こちらは明治時代初期に写された、正門石橋が架けられる以前に存在した「西の丸大手橋」の写真。
江戸時代までは重たい乗り物が通らなかったので木造の橋でも問題なかったのだろうが、明治時代になってから馬車などが通るようになった為に、石橋や鉄橋に姿を変えていったのだろう。
皇居外苑はこのように至る所に緑が植えられていて、しかも丁寧に芝生も管理されている為に、とても気持ちの良い場所ともなっている。

それだけ税金が使われているぜい!
坂下門にて
そして掘り沿いに北側に進んで行くと、また大きな門が見えてくる。
さすがに大きな江戸城跡だけに至る所に門が設置されているけど、門の先の西の丸内は皇居となっている為に、厳重な警備体制となっている。
ちなみにこの坂下門の前でも、幕末に『坂下門外の変』という老中暗殺未遂事件が起きた場所でもあった。
これは「桜田門外の変」が起きた約2年後の出来事で、井伊直弼の開国路線を継承した老中:安藤信正が、攘夷派だった水戸浪士達に襲撃された。
しかし、「桜田門外の変」の後に警備が強化された江戸城内で、襲撃した人数も少なかった為に、襲撃犯は全員討ち取られて、老中:安藤信正も命に別状はなかったという。

昔は暗殺事件が多かったぜい!
この坂下門も昔の門らしく、二段構えの桝形門となっていたが、外側の高麗門は今では見られない。
また、この坂下門も江戸時代の姿から90度回転した東西に向く形に改造されているようで、江戸時代の姿のまま残っているという訳でもないようだ。
その坂下門の奥に見えている大きな建物が「宮内庁」で、名前だけはよく聞く組織である。
このように江戸城跡本丸内に行きたくても、意外と迂回しないと辿り着けない場所になっていた。
事前に本丸跡への入場口を調べていればスムーズに辿り着けたのだろうが、個人的にはウロウロしながら散策した方がより記憶に残るので楽しいのである。

ウロウロして楽しいのは、アンタだけや!(怒)
そんな皇居外苑をウロウロと歩いていると、一画にこのような石垣っぽい形になった「水飲み場」が見えてきた。
日本という国に住んでいる人間の有難さは、”水道水が飲める”事である。
世界中の国では水道水が普通に飲める安全基準を、クリアしていない国が多いからだ。
そんな”水道水が飲める”有難い日本国で、贅沢にもミネラルウォーターを買って飲んでいる人も多いけど、2022年の世界的なインフレもあって、わざわざお金を出してまでミネラルウォーターを飲まずに、水道水を飲むようにしている。

グビグビ・・・皇居の味がする・・・?

江戸の味がするぜい!
そして堀沿いに進んで行くと、また警備が厳重な門が見えてくる。
こちらの門は「桔梗門」で、江戸時代初期に建造された門が高麗門もそのままに残っている門となっている。
入口周辺に一般人がウロウロしていたけど、『皇居一般参観ツアー』参加者はこの門から入れるようになっているという。
この桔梗門は登城する大名が桜田門を通ってやって来る門でもあったので、さっき見た桜田門を「外桜田門」と呼んで、この桔梗門を「内桜田門」とも呼んでいたとか。
このように意外と江戸時代の姿が残っていたり、手を加えられていたりで、詳しい解説を聞かないとイマイチ理解できない江戸城跡でもある。
こちらの櫓は「桜田巽二重櫓」とも呼ばれる”隅櫓”で、これも江戸時代から残る建造物。
ただ大正時代の関東大震災で倒壊してしまったが、その後に復元されている建物でもある。
元々は周囲を監視する為の櫓であったが、今では江戸城跡を彷彿とさせる雰囲気を醸し出す櫓ともなっている。
こんな旅はまた次回に続きます!
よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!
↓↓↓↓東京旅:一覧ページ↓↓
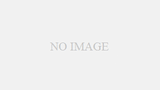
2022年11月上旬に訪れた、2泊3日の東京旅です。































